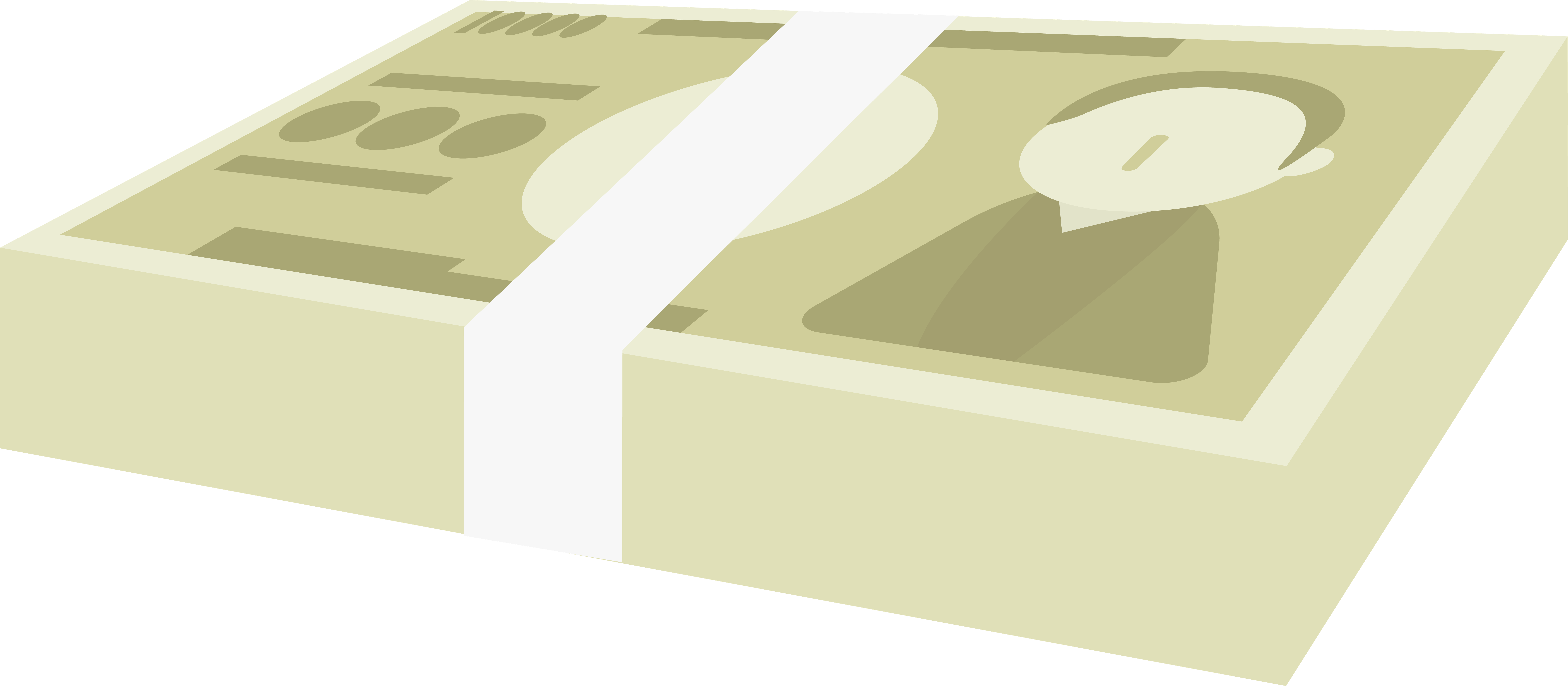A.法人が役員に対して支給する給与のうち一定の給与に該当するものは、不相当に高額な部分の金額を除き、損金に算入されます。
ちなみに、退職給与は、不当に高額な部分の金額を除き、損金に算入されるのが原則です。
1.税制改正前の役員に対する給与の取扱い
平成18年度の税制改正前は、役員に対する給与が「役員報酬」(月給等の定期の給与)、「役員賞与」(臨時的な給与)、「役員退職給与」に区分され、法人税法上、役員報酬と役員退職給与は原則として損金算入、役員賞与については損金不算入とされていました。ただし、役員報酬と役員退職給与について不相当に高額な部分は損金不算入、役員賞与について使用人兼務役員に支給する使用人分の賞与で一定の要件に該当するものは損金算入とされていました。
2.役員給与のうちで損金算入が可能なもの
平成18年度の税制改正により、役員報酬や役員賞与等の、法人が役員に対して支給する給与は、法人税法に「役員給与」としてひとくくりに規定されました。
この改正については、次のことがその背景にあります。
・会社法第361条(取締役の報酬等)に「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」と定められ、役員報酬も役員賞与もこの規定を基に職務執行の対価として扱われることとなったこと。
・企業会計においても、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会、平成17年11月29日)で「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する」とされたこと。
そして、「ひとくくりに規定され」たというのは、平成19年4月1日以降に開始する各事業年度において、「法人が役員に対して支給する給与」のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入されないという規定となったということです(ただし、同族会社については、利益連動給与の損金算入は認められていません)。定期同額給与、事前確定届出給与、又は利益連動給与に該当する場合には、不相当に高額な部分の金額以外は損金に算入されます。
定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与として認められる要件は次の通りです(ただし、不相当に高額な部分は損金不算入となります)。
(1)定期同額給与
・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること。
・その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること(ただし、業績の著しい悪化に伴う減額等の場合に関する一定の例外規定もあります)。
・事前の定めがあること(その内容に関して議事録等を作成しておくことが重要です)。
(2)事前確定届出給与
支給時期及び支給額が事前に定められていて、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出していること。
(3)利益連動給与
・全ての業務執行役員に支給すること。
・算定方法が、全ての業務執行役員について同一であること。
・算定方法が、有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基にした客観的なものであること。
・支給限度額が定められていること。
・同族会社ではないこと。 等
なお、医療法人については、利益連動給与として認められる要件を満たすことはないと考えられま
す。
利益が生じたことによって事業年度の途中で増額するような役員給与は、定期同額の要件を満たさ
ず、全額が損金不算入になります。損金算入できる役員給与は、かなり限られているといえるでしょ
う。
3.役員給与から除かれるもの
上記2の「法人が役員に対して支給する給与」からは、次に掲げるものは除外されます。
(1)退職給与
(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの
(3)上記(1)・(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの
(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによってその役員に対して支給するもの
ちなみに、上記(1)の退職給与は役員給与には該当しませんが、以前と同様に「不相当に高額な部分の金額」を除いて原則として損金に算入されます。
4.使用人兼務役員の要件
上記3で述べた通り、役員に対する給与のうち、使用人兼務役員に対して支給する「使用人としての職務に対する部分」については、この規定は適用されません。
医師以外の役員については、使用人兼務役員となる人もいるのではないでしょうか。理事長の奥様でも、使用人兼務役員に該当する場合があります。
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人のことですが、次に掲げる役員は使用人兼務役員とはなりません(法人税法施行令第71条)。
(1)代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
(2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
(4)取締役(委員会設置会社の取締役に限ります)、会計参与及び監査役並びに監事
(5)同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員
医療法人については、上記(5)は無関係であるといえます。なぜなら、医療法人は医療法を基に設立された法人であって、医療法では剰余金の配当が禁じられていること等から、会社法を基に設立された営利法人とは違いますので、医療法人は同族会社には当たらないからです。
適切な役員給与はどのような程度であるのかについては、実務上、役員の職務内容や、医療法人の収益状況、他の使用人に対する給与との比較により決まります。
5.医師である理事に対する給与決定のポイント
(1)常勤か非常勤か、職務内容に応じた給与か
高額を非常勤の理事に支給した場合、否認されることがあります。
(2)医療法人の収益状況や他の使用人に対する給与に照らして適切か
法人の決算内容に照らして支給額が不自然ではないか、他の使用人と比較して極端に高額ではないか等を検討する必要があります。
(3)同種同規模の医療法人における役員給与との比較
同種同規模の医療法人における役員給与と比較して極端に高額である場合、否認されることがあります(院長が他の法人の役員の給与額を知っているとは考えにくいことから、多くの事例を熟知している顧問税理士等に相談されるのも一つの選択肢となります)。
6.医師以外の理事に対する給与決定のポイント
上記5と基本的には同じであるといえますが、医師である理事の給与より医師以外の理事の給与が高額であるということはほぼないと考えられますので、留意が必要です。